起承転結の意味がわからなくても、名前くらいは聞いたことあるんじゃないかっていうくらい有名ですね。漫画や小説などのストーリー構築だけじゃなく、小学生の宿題の読書感想文だとか大学のレポートだとかビジネスなんかにも利用されてたりしますね。
漫画のストーリーを創る基本中の基本である「起承転結」とは、どのようなものなのかを書き記していこうと思います。
そもそも起承転結とは?
もともとは、4行からなる漢詩の絶句の構成のことだったのだとか。そこから派生して文章やストーリーなどを4つに分けたものも起承転結と呼ばれるようになったとのこと。
海外では三幕構成と呼ばれる序破急が一般的で、起承転結は中国から来たこともあり日本など一部の地域に根付いているストーリー構築の技術。
漫画のストーリーに起承転結を使う意味
 では、ストーリー構築において起承転結でどのようなことができ、どんな意味があるのかを紹介していきます。
では、ストーリー構築において起承転結でどのようなことができ、どんな意味があるのかを紹介していきます。
起承転結はストーリーを作る基本ではあるものの、単なる骨組みであると考えるのがポイント。読者が面白い!と唸るのとは別の要素であり、キャラクターなどで肉付けしていく必要があります。
漫画のストーリーを考える時に、筋書きの組み立てを行うのが「起承転結」!
起承転結のそれぞれの意味と書き方を紹介
起承転結はそれぞれで役割というものを持っています。起、承、転、結の構成をみていきましょう。
物語の始まり「起」
言わずもがな「起」は字のごとく、漫画のストーリーの始まりです。世界観の説明や主人公などの主要キャラクターを登場させます。その漫画の世界に住んでいるキャラクターたちがどんな日常を送っているのか、普段なにをしているのかっていう入りですね。
一番長い「承」
漫画の物語で一番長い部分になります。事件が起こり、日常が非日常へと変わっていきます。そして、その解決へと向かっていくパート。
例えば、平和な街だったのに急にゾンビだらけになってしまうなどが起⇒承への移り変わりです。主人公たちの奮闘が描かれます。
映画を見ているとわかりやすいです。大体20分~30分で事件が起こるはずかと。
クライマックスとなる転へつなぐ架け橋であり、伏線を張ったり、キャラクターが葛藤したりと下準備が重要な部分です。ミステリーなんかだと、主人公が証拠を集めて情報がまとまるといった具合。
承がよくわからずイメージできないという人が多いですね。
起こった事件へどう対処していくかといった主人公たちの奮闘部分と思っておくといいかも。
ミステリーなら証拠集め、モンスターパニックなら武器や薬の調達、恋愛ならデートと心の葛藤などでしょうか。
クライマックス「転」
主人公たちが目的に向かい解決する瞬間が「転」です。まさにクライマックスであり、漫画のストーリーで一番盛り上げなければいけない部分です。
承の部分で例に出した殺人事件であれば犯人に証拠を突き付け逮捕、ゾンビであればワクチン入手などになります。
これまで溜め込んできたものを爆発させるようなイメージで転を描けたら理想ですね。伏線をバシバシ回収して爽快に犯人はお前だー!みたいな。
物語の終わり「結」
漫画などの物語自体は「転」までで完結します。が、そのままでは読者は放り投げられた気分になってしまいます。その後はどうなったのかをこの「結」で描きます。全てを描かず謎を残すというのも後を引いて面白いですね。
描くといっても本当に少しで大丈夫です。逆に長々としていると読者は「ん?あれ?まだ物語続くん?」みたいになっちゃうのでサラッと締めましょう。
ゾンビなどのモンスターパニックであれば転で一掃した後に家族とハグするとか。
起承転結の配分はある程度決まっている
 起承転結は4つの構成に分かれているので全てをきれいに4等分したくなりますが、そうすると詰め込みたい部分に情報を入れることができずストーリー展開のテンポが悪くなります。4コマ漫画だときっちり4等分といった感じですが・・・。
起承転結は4つの構成に分かれているので全てをきれいに4等分したくなりますが、そうすると詰め込みたい部分に情報を入れることができずストーリー展開のテンポが悪くなります。4コマ漫画だときっちり4等分といった感じですが・・・。
で、実はある程度、起承転結のページ配分が決まっているんです。マラソンをイメージしてみて、序盤から全速力なんていうことないですよね。
その配分は、「起が20%」「承が45%」「転が30%」「結が5%」くらいに考えてもらえればいいと思います。
読み切り漫画で指定される32ページを元に配分を考えると・・・「起が6~8ページ」「承が12~16ページ」「転が6~10ページ」「結が1~2ページ」くらいになります。
僕自身の起承転結の配分
自分は「起8ページ」「承が16ページ」「転が7ページ」「結が1ページ」くらいで漫画をいつも描いてました。自分がバランスよく漫画を描ける配分が見つけられるといいですね。枠が決まるとはめ込んでいく感じになるので作業的にも思考的にも楽になります。
正直、結は漫画などにおける余韻なので1~2ページ、むしろ1ページの半分でもいいくらいです。上記でも書きましたが、多すぎると読者はくどいと感じてしまうものなので・・・。かと言って、何もないと放り出されてしまう気分になるので入れないわけにはいきません。
例としては転で犯人を逮捕し、結で犯人を乗せたパトカーを見送るといったくらいあっさりと。
ちなみに、ここにある配分は飽くまで例なので、個人個人、作品ごと、それぞれで「これだ!」っていうペースが変わってくると思います。
例文で考える起承転結
起承転結の何となくの意味はわかったけど、いまいちピンとこない・・・という人はこれからあげていく例文を元にしてみると理解しやすいかな~と思います。
例文:桃太郎の起承転結
 たぶん誰もが知っているであろう物語の桃太郎で起承転結を具体的に説明。
たぶん誰もが知っているであろう物語の桃太郎で起承転結を具体的に説明。
- 起⇒おじいさんとおばあさんの登場、桃から桃太郎が誕生。
- 承⇒村の人々を苦しめる鬼退治に出かける桃太郎、犬・猿・雉を仲間にし鬼ヶ島に向かう。
- 転⇒鬼との激しい戦いの末に勝利!
- 結⇒奪われた村のお宝を取り戻し、村に平和がやってくる。
非常にわかりやすく説明しやすいストーリーです。何が起き、何をしに行き、結果を残し、その後どうなったかという一連の流れができてます。
例文:ウサギとカメの起承転結

ウサギとカメが競争をするというお話を例文に起承転結を考えていきます。
- 起⇒小馬鹿にするウサギと真面目そうなカメが登場し、言い合いから競争をすることになる。
- 承⇒レースがスタートし、ウサギがすごいスピードで引き離しカメを引き離すが、ウサギは勝利を確信して木陰で居眠りしてしまう。
- 転⇒眠っているウサギをカメが追い越し勝利。
- 結⇒表彰されるカメとがっくりするウサギ。
相反する登場キャラクターであるウサギとカメが競争するということになり、油断したウサギが負けるはずのないカメにやられるというカタルシスもあるストーリーです。
例文:赤ずきんちゃんの起承転結

少し長い童話の赤ずきんちゃんの起承転結を考えていこうと思います。
- 起⇒赤い頭巾を作ってくれたおばあちゃんが病気と聞き、お見舞いに行くことになります。
- 承⇒オオカミと出会い無邪気な赤ずきんは予定を全て話してしまいます。オオカミは先回りしておばあちゃんを食べてしまい、赤ずきんも騙して食べようとします。
- 転⇒赤ずきんもオオカミに食べられてしまうが、通りすがりの木こりに助けてもらい、オオカミのお腹に石を詰め込み仕返しをします。
- 結⇒オオカミはいなくなり森に平和が訪れます。
オオカミなどの伏線が張ってあったり、赤ずきんとオオカミの攻防があったりとまとまっているストーリーです。まぁ最後の通りすがりの木こりとか食べられて生きている二人とかはアレですけど・・・w
漫画における起承転結の使い方のコツ
漫画のストーリーを起承転結に上手くはめ込むために理解しておくべきものは役割と配分ですね。
まとめのような感じになりますが・・・
役割は、起では何をすればいいのか、承では何が起きるのかなどそれぞれの区間ごとに何をしたいのかを明確にしておく必要があります。
配分はどれだけの尺をどこに割くのかをある程度決めて、物語がだれないようにします。
この2つを考えながら漫画のストーリーを作れば起承転結の効果を十分に発揮できると思います。
最初のうちはなかなか難しいですが、数をこなすと頭がだんだんそういった作りになっていって自然と組み込めるようになっていきます。映画などを見ている時に意識すると、より一層身につきやすいと思うので、どこが起から承への切り替わりなのか、クライマックスである転はどこなのかなどを考えるといいと思います。
起承転結を重要視せず骨組みと考える
起承転結は、飽くまでも漫画のストーリー創りにおける骨組みなので面白さとは違います。漫画の面白さは、魅力的なキャラクター、クライマックスで読者が感じることができるカタルシス、華麗なる伏線、痺れるセリフなど様々なファクターが必要になります。なので、起承転結に当てはめなきゃ当てはめなきゃ・・と必死になるのはむしろ良くないと思います。
しかし、結局のところ、自分がいくら面白いと思った漫画でも、読者がつまらないと言ってしまえば面白くない漫画となってしまいます。
でも、全てが同じ人間じゃないので仕方ないこと!自分が面白いと思ったものを漫画として描くのが一番だと思ってます。
ぜひとも起承転結というツールを使って漫画作りの役に立ててみてくださいね。


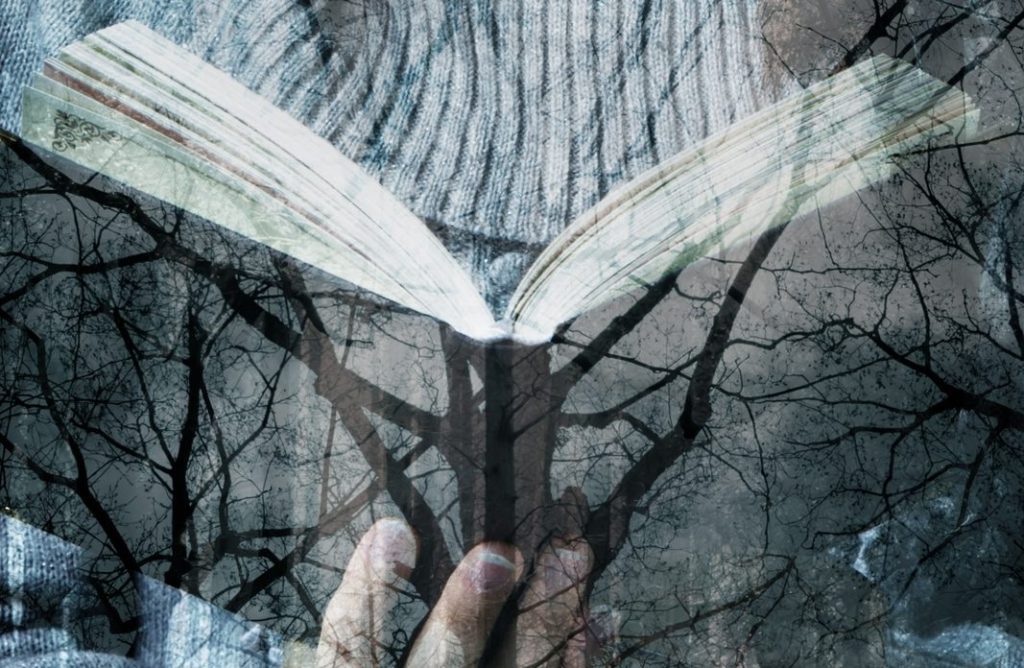











どうも、ぷ~ちんです。
起承転結は、漫画のストーリーを構築する便利なツールとして認識するのが一番いいのかなというのが僕の考えですね。